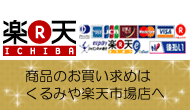「ご家庭で簡単!手当て法」のコーナーでは、昔からおばあちゃんの知恵として重宝されて来た、食養法(正食法)をご紹介致します。
薬ではないので、副作などの心配も一切なく、自然治癒力を低下させる事もありません。自然の恵みがいっぱい詰まった食べ物を使って、古来から伝わるありがたい知恵で手当てする。。。
そんな素晴らしい方法があるんです。.:*・゜☆
|
 |
●今回は玄米による手当て法のご紹介です●
玄米には解毒作用があります。玄米のもつこの力を、よりよく発揮させる玄米を使った正食手当て法をご紹介します。
治病のための食事作りに、大事なことは心をこめて作るということであり、たとえば玄米クリームや玄米クリームスープなどを作るときに塩加減が適切でなければ、あかちゃんなどは正直なもので吐き出してしまいます。体液に近い塩加減をすれば、体は抵抗なく玄米クリームなどを受け入れます。このためには経験が必要であり、細心の注意をもって、ていねいに心をこめて作ることです。 |
★玄心(黒炒り玄米スープ)・玄神・玄米クリームスープ・玄米クリーム・生玄米・炒り玄米・玄米茶・玄米粥三種(干柿入り玄米粥・椎茸入り玄米粥・干しミミズ入り玄米粥)★
|
| ● 玄心(黒炒り玄米スープ) ● |
●材料●
玄米…一合
塩・・・少々
水・・・一升
|
●玄心の作り方●
1.玄米は洗わずにそのままフライパンや鍋に入れ、中火よりやや弱い火で根気よく炒る。
2.炒っていて煙が出てもそのままの状態を続けると、泡が吹いたようになり玄米が鍋に焦げついてしまうので、煙を出さないように注意する。
3.一時間ほど気長に炒り、玄米の中心部まで火を通す。玄米に爪を立ててみて、ポンと二つに割れ、割れ口が濃いこげ茶色になったら炒りあがりです。
4.分量の水を加え塩を少々(できあがったときにに塩味を感じない程度)を加える。
5.じっくりと煮詰めて、水の量が三分のニほどになったら火を止める。
6.上澄みをとり飲用する。玄米一合から約三合半の黒炒り玄米スープができます。
|
※黒炒り玄米スープ一合を一日分として飲む。お茶代わりにするのであれば、三合半を一日分としてもよいでしょう。
※食べ物がなにものどを通らない重病人は好きなだけとってもよいでしょう。
|
● 玄神 ●
カゼの原因というものは、はっきりしません。
カゼをひいて熱がなかなか下がらないとか、下痢をしたとか腰が痛むとか、それらの症状についてなにか良い手当て法はないものか。
下痢とか腰が痛む場合は葛湯、生姜シップなどのしかるべき手当てをすれば、すぐに治まるが、熱については、従来の手当て法であるリンゴ汁、ダイコン湯、レンコン湯などの手当てをしてもなかなか治まらないカゼがあります。
普通のカゼであれば、ピタリと熱が治まるのに、これらの手当てをしてもなかなか熱が下がらず、いつまでも微熱がつづくという場合があります。そんなときいままでリンゴ汁やダイコン湯、シイタケスープなどいろいろな熱を下げる手当て法をしてもつづいていた微熱が、たった一回の玄神の服用で熱がピタリと治まることがあります。
ぜひ、お試しください。
●材料●
玄米‥1/2カップ
水‥4カップ
玄米:水=1:8の割合
|
●玄神 の作り方●
1.玄米は洗わずそのまま空鍋で強火で炒る。
2.焦げ茶色になり、次に黒くなって玄米に粘りが出て煙が出てきたら、火を止める。火からおろしても、しばらくはくっつき合わないように混ぜておく。
3.分量の水の中に2.を加え、水分が三分の二くらいになるまで煎じる。
|
|
● 玄米クリームスープ ●
玄米クリームは断食をして復食を始めるときに一番適した食物です。
滋養があって、しかも胃腸に負担をかけないためです。また、あらゆる病人の飲み物としても最適で、微熱のあるときは熱を下げる効果もあります。
母乳のかわりや離乳食にももってこいです。アトピー性鼻炎などの乳幼児を持つお母さんで「ミルクはやめて、豆乳を与えているのに、なぜ?」という方がいますが、豆乳は陰性食品でありこれを玄米クリームスープに変えると、よくなります。
|
●材料●
玄米・・・一合
塩・・・少々
水・・・一升
|
●玄米スープ の作り方●
1.玄米を洗い水を切っておく。
2.フライパンや鍋で狐色になるまで炒る。
3.2.に分量の水を加え、ほんの少し塩を入れ、煮詰める。
4.約一〜二割、水分が減れば火を止める。
5.4.を木綿袋に入れ、しっかりともみ出す。一度すり鉢でつぶしてから、袋に入れると漉しやすい。
6.もみ出した重湯をいただく。
|